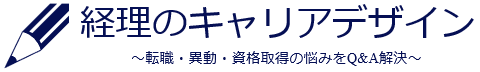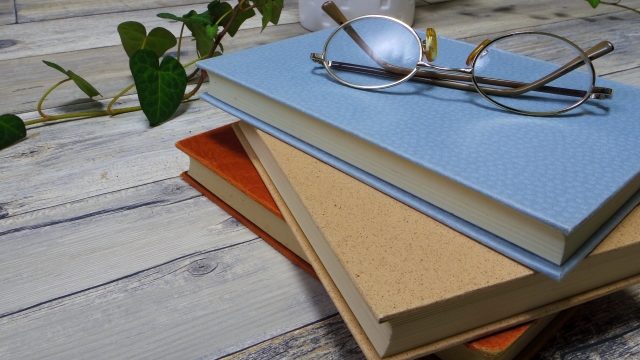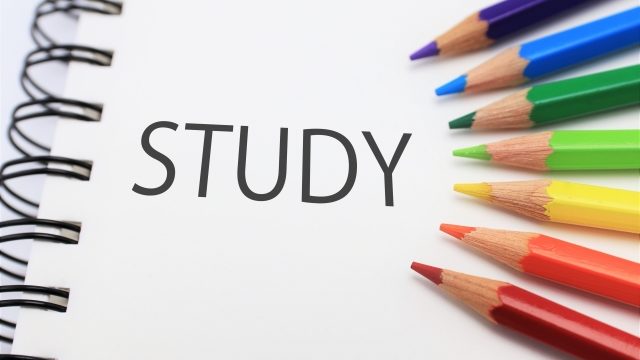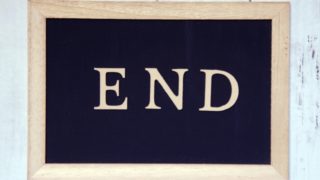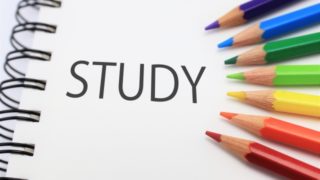理論と実務を兼ね備えた“経営企画の最終形態”
「中小企業診断士を取ったけど、MBAも気になる」
「MBAを取ったけど、イマイチ実務で活かせていない気がする」
せっかく苦労して難関資格を取得したのに、そんな声をよく聞きます。
実は最近、経営企画・管理部門・コンサル業界で増えているのが、
“中小企業診断士×MBAのダブルホルダー”です。
一見、学ぶ範囲が重なっているように見えますが、
この2つを組み合わせることで、理論・実務・人脈・信頼性の全てをカバーできる強力なキャリアになります。
Contents
中小企業診断士とMBA、それぞれの得意領域
まずは2つの資格・学位の「得意分野」を整理しましょう。
■中小企業診断士
・経済産業省認定の国家資格
・経営全般(財務・人事・マーケ・運営管理など)を網羅
・実務寄りの課題解決力を重視 ・中小企業の経営支援や内部改善に強い
■MBA(経営学修士)
・国内外の大学院で授与される学位
・ケーススタディ中心の“経営判断力”を磨く
・チームでのディスカッション・リーダーシップを重視
・グローバル経営・戦略立案に強い
つまり、
中小企業診断士は「現場実務の専門家」、MBAは「戦略のリーダー」という関係性です。
この2つを掛け合わせると、経営企画やCxO(経営幹部)を目指すうえで“穴のない知識構成”を作ることができます。
理論 × 実務で経営企画・経営管理に圧倒的な強み
経営企画の現場では、次のような2種類のスキルが求められます。
1️⃣ 現場を数字で動かす力(診断士的スキル)
2️⃣ 会社全体を俯瞰して意思決定する力(MBA的スキル)
たとえば、経営計画を作るとき。
MBA的な戦略理論だけでは「絵に描いた餅」になりがち。
一方で、診断士的な実務知識だけでは「経営層の意図」を読み切れません。
両方の視点を持つことで、
「経営戦略を、現場で実行できる形に落とし込む」ことができるのです。
これはまさに、経営企画の理想像。
経営会議で社長の意図を読み、現場数字に落とす。
この“翻訳力”を持つ人材が、どの企業でも引っ張りだこです。
ダブルホルダーが評価される3つの理由
1️⃣ 経営層との共通言語を持てる
MBA的な理論・フレームワークを理解していることで、社長・役員との議論がスムーズになります。
ロジカルな経営分析資料を提示できる点も強みです。
2️⃣ 現場感覚を失わない
中小企業診断士の知識は「現場のリアル」に強い。
会計処理・原価管理・人事制度など、会社を支える実務の裏付けがあるため、
戦略とオペレーションの両立ができる。
3️⃣ 転職・昇進での“信頼性”が高い
経営企画・CFO候補ポジションの採用では、資格やMBAを“信頼の証”として見る企業が多い。
「理論も実務もわかる人」という印象は非常に強力です。
実際のキャリア事例
■Aさん(メーカー経理 → 経営企画部長)
30代で中小企業診断士を取得し、40代で国内MBAへ進学。
診断士で実務力を高め、MBAで経営層視点を磨いた結果、
経営企画部長として経営計画と資金戦略の両面を担当。
Aさんは「資格取得の順序を逆にしなかったのが良かった」と語ります。
中小企業診断士→MBA取得がオススメとのことです。
■Bさん(中小企業コンサル → スタートアップCFO)
独立診断士として活動しながら夜間MBAを修了。
財務戦略と事業分析の両方を得意とし、スタートアップCFOに転身。
「どちらか片方だけならここまで信頼されなかった」とコメント。
大変だけど、ダブルホルダーのメリットは大きそうです。
ダブルホルダーを目指す際のポイント
中小企業診断士とMBA、両方を狙うなら順序が重要です。
おすすめはこのルート👇
中小企業診断士 → MBA
まず診断士で経営の全体像と実務感を掴み、
その後にMBAで理論と人脈を広げる流れが最も効率的。
逆にMBAから診断士に行く場合、理論先行でモチベが下がることがあります。
また、MBA在学中に診断士試験の学習を並行するのは非常にハード。
両立を狙う場合は通信MBA+診断士二次試験免除制度(実務補習経由)を活用すると良いでしょう。
転職市場での評価は?
リクルーターや人材エージェントの評価では、
「中小企業診断士×MBA」は次のようなポジションで引く手あまたです。
- 経営企画/経営戦略室
- CFO・管理本部長候補
- 経営コンサルティングファーム
- ベンチャーCFO補佐・経営管理マネージャー
特に40代以降のキャリア再構築では、
“資格と学位のダブルブランディング”が効く。
単なる資格マニアではなく、「経営を動かせる実務家」として扱われるからです。
中小企業診断士とMBAの資格取得は学習範囲が被るから取得しやすい
中小企業診断士とMBAの大きなメリットの一つは、
学習範囲がかなり重なっているという点です。
両者とも「経営全般を体系的に学ぶ」ことを目的としているため、
以下のような分野ではほぼ共通しています。
・財務会計・管理会計
・経営戦略・マーケティング
・人事組織論
・オペレーション・ロジスティクス
・経済学・経営分析
診断士試験で一度学んだ内容は、MBAでもほぼそのまま活かせるため、学習の効率が非常に良いのです。
たとえば、診断士の「企業経営理論」で学んだSWOT分析やポーターの5フォース分析は、
MBAの授業でも頻繁に登場します。
会計論に関しても、管理会計・原価計算・財務分析の基本構造はほぼ同じ。
つまり、診断士で“幅広い基礎”を固めてからMBAで“応用”を学ぶと、最小の努力で最大の成果を得られるわけです。
特に国内MBAでは、診断士の一次試験・二次試験で培った知識が
入学後のディスカッションや課題で即戦力として使えるケースが多く、
「授業の理解スピードが早い」と感じる受講生も多いです。
さらに診断士資格を持っていると、
MBA入試(特に社会人MBA)で「経営知識を既に持っている」ことが評価され、
出願書類や面接でアピール材料になる点も見逃せません。
資格取得の順序と勉強スケジュール例(最短でダブルホルダーを目指す)
中小企業診断士 × MBA のダブルホルダーを本気で目指す場合、
もっとも効率的なのは、次の順序です。
① 中小企業診断士 → ② MBA の順番で取得
理由はシンプルで、
診断士の学習内容がMBAの基礎になるため、MBAの負担を大幅に減らせるからです。
特に社会人が仕事と両立しながら両方を取るなら、“順番”が非常に重要になります。
▼ステップ①:中小企業診断士の学習(1〜1.5年)
診断士は「幅広い経営知識」を体系的に学ぶための最高峰資格。
まずは以下の一次試験科目で基礎を固めます。
- 経営戦略・組織論
- 財務会計
- 経済学
- 運営管理
- IT/システム
- 法務
- 中小企業政策
これらの内容が MBAの授業でそのまま使える土台 となります。
また、二次試験で鍛えられる「論理的思考」「事例分析力」は、MBAのケーススタディと完全に相性抜群。
診断士で鍛えた思考方法が、MBA入学後の武器になります。
▼ステップ②:MBA入学(2年制 or 1年制)
診断士で基礎を固めた状態でMBAに進むと、
- 授業理解が早い
- ケースディスカッションに強い
- 財務の授業でつまずきにくい
- レポート・プレゼン能力が飛躍的に伸びる
という「相乗効果」が生まれます。
さらに診断士資格があると、
社会人MBAの入試で評価されやすいというメリットもあります。
▼おすすめのスケジュール例(社会人向け)
【1年目】 ・診断士一次試験の勉強スタート(週10〜15時間目安)
【2年目】
・診断士一次合格 → 二次試験まで勉強
・同時にMBA出願準備を進める(志望理由書・英語)
【3年目〜】
・診断士合格 → MBA入学
・MBAで専門領域を深掘り(戦略/財務/組織など)
こうした「診断士 → MBA」の流れを踏めば、
専門性と実務能力がバランスよく高まり、
経営企画・コンサル・事業責任者などの“経営サイドのキャリア”に強い人材になれます。
まとめ:理論と実務をつなげられる人が最強
中小企業診断士とMBA。
どちらか一方でも十分に価値がありますが、
両方を取得することで「経営の現場」と「戦略の空」を自由に行き来できる存在になれます。
つまり、ダブルホルダーは
“経営の翻訳者”であり、“企業価値を高める実務家”。
もしあなたが経営企画やCFOを目指しているなら、
この2つの組み合わせは“最強のキャリア投資”になるはずです。