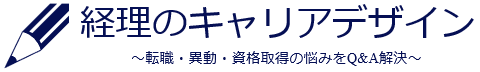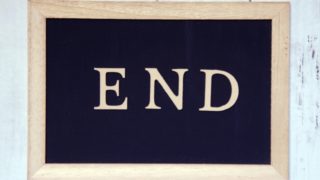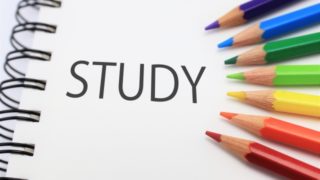「親会社から子会社に出向するなんて、キャリアの幅も広がって良い経験になるんだろうな」
そんな風に思われがちですが、実際に出向を経験したCさん(30代・総合職)はこう語ります。
「正直、ツラいことの方が多かったです。華やかに見えるけど、実態は“孤独と板挟み”の連続でした。」
ここでは、Cさんの体験をもとに、親会社から子会社へ出向した社員が直面するリアルを紹介します。
Contents
子会社ではプロパー社員からの“よそ者扱い”が続く
Cさんが配属されたのは、親会社100%子会社の管理部門。
最初の頃から、プロパー社員の冷たい視線を感じました。
「どうせ数年で親会社に帰るんでしょ」
「また“お偉いさんの代理人”が来た」
仕事を一緒にしていても、腹を割ったコミュニケーションが取りにくく、常に「外様」という立場を意識させられたといいます。
親会社の意向と現場の板挟み
出向者の役割のひとつは、親会社の意向を子会社に伝え、実行させることが重要です。
しかし、子会社の現場は必ずしも親会社の指示を歓迎しているわけではありません。
Cさんも「無理なコスト削減案」を伝えたとき、現場からの強い反発に遭いました。
親会社に逆らうわけにはいかない…
子会社の現場の声も理解できる…
その板挟みの中で、自身に与えられた役割に対して立ち振る舞うのがツラく…
精神的にすり減っていったと振り返ります。
ツライ…子会社プロパー社員からのライバル視
子会社の管理職ポストは、出向者で埋まることが多いのが現実です。
そのため、子会社プロパー社員にとって出向者は「自分たちの昇進を奪う嫌な存在」。
Cさんも子会社での課長職に就いた瞬間から、周囲の空気が一層冷たくなったといいます。
「結局、親会社の看板があるからそのポジションに座れたんでしょ」
そう言われ、実力で認められているわけではないことに苦しみました。
子会社プロパー社員は親会社との年収待遇の違いを理解している
出向者が最も居心地の悪さを感じるのは、圧倒的な年収や待遇の差です。
子会社プロパー社員は、自分たちよりも短い在籍期間で管理職に就き、さらに給与水準も高い出向社員の存在を敏感に察知しています。
「同じ課長でも、年収は数百万円違う」
そんな現実を知っているからこそ、心のどこかに不公平感や嫉妬が生まれやすいのです。
出向社員自身も待遇の違いを口にすることはできず、気まずさを抱えたまま働く日々が続きます。
子会社プロパー社員は当然ながら子会社の現場のことを理解していますし、自社への愛情もある人が多いです。中には親会社社員以上に優秀な人もいますが、それでも親会社出向社員のほうがずっと待遇が良いのが現実。
これを理解している子会社プロパー社員からの視線は常に親会社出向社員を苦しめるのです…
わからなくて当然なのに…親会社出向社員は即戦力が期待され、質問もしにくい現実
もうひとつの厳しい現実は、即戦力であることを求められるプレッシャーです。
親会社から「エース候補」として送り込まれることも多いため、子会社では「来た瞬間から何でもできる人材」と見られがち。
しかし実際には、子会社ならではの業務ルールや慣習があり、最初から完璧に理解することは不可能です。
それでも「そんなことも知らないの?」と見られるのが怖く、素直に質問できない…。
Cさんも、「聞きにくい」「教えてもらいにくい」雰囲気の中で孤独を深めたといいます。
本当は“わからなくて当然”なのに、それが許されない空気こそ、出向社員の精神的な負担を大きくしています。
親会社に戻っても待っている“微妙な評価”
「数年頑張れば親会社に戻れるから」 そう思って耐えていたCさんですが…
出向から戻った後の現実も厳しいものでした。
子会社での成果は、親会社では評価されにくいのです。
「子会社でやってたことは、本社のスケールでは当たり前」
「結局、調整役をしてただけでしょ」
そう片付けられてしまい、昇進スピードは同世代より遅れを取る結果に…。
出向経験をプラスに変えるには?
Cさんは苦しい経験を経て、ようやく前向きに捉えられるようになったと言います。 出向経験をプラスに変えるポイントは次の3つ。
・グループ全体の構造を理解し、親会社と子会社の“橋渡しスキル”を磨く
・プロパー社員と信頼関係を築き、「よそ者」から「仲間」へと立ち位置を変える
・親会社に戻ることだけをゴールにせず、転職市場でも通用する実績を意識する
まとめ:親会社から子会社への出向はキャリアの分岐点になる
親会社から子会社への出向は、外から見ればキャリアの華やかなステップに思えます。
しかし実態は「孤独」「板挟み」「評価されにくい」という厳しい現実が待っています。
ただし、そこで得られる経験もまた貴重です。
グループ全体を俯瞰できる力や、異なる立場の人を調整する力は、後々のキャリアに必ず活きてきます。
「出向=キャリアの終わり」ではありません。
それをどう活かすかは、自分次第なのです。